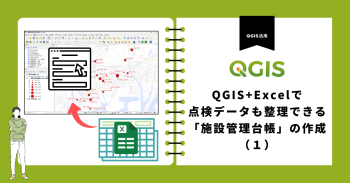エアロトヨタコラムColumn
- エアロトヨタ株式会社 TOPページ
- 知る・楽しむ
- エアロトヨタコラム
- 社会を支える、『測る』技術を現場で学ぶ! エアロトヨタ若手社員の測量研修
news
社会を支える、『測る』技術を現場で学ぶ! エアロトヨタ若手社員の測量研修
はじめに:測量について ~社会インフラを支える、測量技術~
「測量」と聞いて、すぐに意味を思い浮かべられる人は多くないかもしれません。
測量とは、地形や構造物の位置・高さなどを正確に『測る』技術です。
この技術によって得られた情報は、林道の新設や防災計画など、社会インフラの基盤として幅広く活用されています。私たちが何気なく歩いている道なども、すべて『測る』ことから始まっています。
測量は、普段見えないところで社会を支える『縁の下の力持ち』のような存在。
正確な測量データがなければ、安心・安全で快適なインフラは成り立ちません。
エアロトヨタでは、空間情報の取得・解析において、長年培ってきた技術と経験を活かし、社会の基盤づくりに貢献しています。
その大切な技術を次世代に継承するため、今年度より「測量技能継承室」を開設。若手社員を対象とした実地研修を定期的に実施しています。
今回のコラムでは、入社1~2年目の若手社員が参加した測量研修の様子を通じて、『地形を測る』という仕事の奥深さと、技術継承の現場をご紹介します。
『The測量!』技術を学ぶ ~研修の目的と背景~
今回の測量研修は、入社1~2年目の若手社員を対象に、測量の『基礎』である「実測(※現地に赴いて、人の手で地形を測ること)」に関する研修を実施しました。
当社が提供する様々な空間情報サービスにおいて、正確な位置情報の取得は極めて重要です。衛星、航空機、ドローンなど、さまざまな測量手法が存在する中で、最も精度の高い手法が「実測」です。
対象物との距離が近く、現地で人の手によって行われる実測は、地形の微細な変化や障害物の位置など、機械では拾いきれない情報を補完する役割を果たす、重要な技術です。
今回の研修では、若手社員に『The測量!』とも言える実測の基本を体験してもらうことで、技術職はデータの基準を理解する力、営業職はお客様の悩みや現場の課題を深く理解する力を身につけることを目的として開催しました。
安全意識を身に付ける
そして、私たちが測量作業の中で最も大切にしていることは『安全に作業をする』ということです。
外で行う測量作業の環境下においては様々な危険が潜んでいます。
そこで、今回の測量研修では安全に作業をする為に「KY活動」「熱中症予防」「熊対策」の3項目について学びました。
KY活動(危険予知)とは「作業開始前に作業内容を確認して、作業中にどの様な危険が潜んでいるか」を全員で確認することです。従事者全員が危険を予知し、安全な行動が出来るようにしっかりとKY活動を行いました。
次に熱中症の予防についてです。
外で作業を行う測量従事者にとって最も発症リスクの高い災害のひとつです。
また、現在の日本は10月でも残暑の残る日々となり、測量作業を行う上で一切の油断は出来ません。その為、測量研修の中では熱中症対策備品を紹介し、万全の準備をして作業を行いました。
最後は、全国各地で騒がれている熊による人的被害への安全対策です。
特に山岳部で作業をする機会の多い現地に関わる測量にとって重大な災害要因のひとつです。
そこで、熊に遭遇したことを想定した「熊スプレー」の実演を行い、それぞれ身をもってその効果を体験しました。
いざ実践!「基準点測量」「水準測量」にトライ
今回の測量研修では測量の基本である「基準点測量」「水準測量」について、実際に測量機材を使った研修を行いました。
基準点測量とは既知の点(座標が分かっている点)を基に新点を設置し、水平位置と高さを求めることです。
今回の研修ではトータルステーション※を使用して現地に設置されている鋲を既知点として新点の水平位置と高さを求めました。
水準測量とはある地点の高さを基準として他の地点との高低差を算出する測量です。
今回の研修では電子レベルを用いて基準点測量と同様に現地に設置されている鋲から各点の高低差を求めました。
※トータルステーション: 距離と角度を同時に高精度で計測できる測量機器
古来の測量法にトライ
江戸時代の地図作成で知られる「伊能図」のような、昔ながらの測量法を現代に再現する取り組みも行いました。
この研修では、測量機材を使用せず、現場にあったポールの長さを基準に、目測や計算を駆使して地形を図面化するという方法に挑戦しました。
測量用の道具や機械に頼らず、限られた条件の中で工夫を重ねながら測ることで、測量技術の奥深さと本質に触れる貴重な体験となりました。
ハンディレーザ「FARO」の体験
カメラやレーザセンサーなどを使って、周辺環境を認識しながら、リアルタイムに自己位置を特定して地図を作る「SLAM技術」を活用した、「ハンディレーザ測量」というものがあります。
そこでエアロトヨタが所持している最新型ハンディレーザ「FARO Orbis premium」の実演を行いました。
これは『誰でも・どこでも・すぐに』使える測量機材であり、
実際に歩くだけで、位置情報を持った地形・地物の3次元点群データが取得できる最新技術です。
測量データの活用(2日目)
1日目に現地で取得してきた様々な測量成果の計算・整理を行いました。
基準点測量や水準測量の成果は計算ソフトや電卓を使って計算し、行ってきた作業の正確性や精度の高さを認識することが出来ました。
最終的に、ハンディレーザ測量の成果と併せて図面データを作成することで、図面作成の大きな流れを体験し、研修終了!
参加者の声を聞いてみました!
今回の実測研修に参加した若手社員からは、さまざまな気づきや学びの声が寄せられました。
『標定点測量の説明に自信が持てるようになった』
実測の理解が深まったことで、撮影業務における標定点の説明がより具体的かつ正確にできるようになり、顧客対応にも自信がついたという意見。
『測量という基盤技術を知ることで、業務全体の理解が深まった』
測量の現場を体験したことで、案件の流れや背景がより明確になり、営業活動や社内連携にも役立つと感じたそうです。
『KY活動の重要性を改めて実感した』
現場に入る前のKY活動は、普段の業務よりも安全意識を高める内容で、今後は慣れによる油断を防ぎ、毎回しっかりと実施する必要性を感じたとのことです。
若手社員たちは、今回の研修を通じて『測る』技術の奥深さと安全意識の重要性を実感し、今後の業務に積極的に活かしていきたいという前向きな姿勢を見せていました。
終わりに:見えない仕事が社会を支える
技術の進歩でますます便利な世の中になった今だからこそ、私たちは測量実習を通じて地図作りの基本をしっかり学び、社会インフラを支える『縁の下の力持ち』としての技術を日々磨いています。
測量は、災害対策や都市計画など、安心・安全な社会づくりに欠かせない技術です。
エアロトヨタは、これまで培った確かな技術を次世代へ継承し、安心・安全な社会づくりに貢献していきます。
これからの社会を支える技術者の一人として、あなたも“測る”という仕事の奥深さに触れてみませんか?
執筆者プロフィール
1987年生まれ
民間測量会社に10年間在籍し、主に地形測量や用地測量を担う
2023.9 エアロトヨタに中途入社
資格:測量士(H28-431)